top of page

The knowledge of all things is possible.
.jpg)
ブログ管理人:田中ゲイリー
東京都出身。東京大学卒業後、都内金融機関にて投資銀行業務に従事。その後、米国へ留学しMBA(経営学修士)を取得。現在は、上場企業にて経営企画業務に従事する傍ら、副業としてITスタートアップにてCFOとして関与。
Blog Author: Gary Tanaka
CFO of the IT venture company (Data Analytics)
Finance / Corporate Planning / Ex. Investment Banker
University of Tokyo (LL.B) |
University of Michigan, Ross School of Business(MBA)
Tokyo, Japan
お問い合わせ |
検索


書評:『2040年の未来予測』 成毛 眞
この本は、今日の延長線上に未来があるという前提で、あらゆるデータから導かれるありのままの未来を描く。 全般的に非常にモデレート(穏健)な内容であり、読んでいて違和感のないストーリーであるが、ベンチャーキャピタリストが書いたような未来予測本のような刺激はない。...


書評:『FACTFULNESS(ファクトフルネス)10の思い込みを乗り越え、データを基に世界を正しく見る習慣』ハンス・ロスリング
本書のタイトルである『FACTFULNESS』とは、データや事実に基づいて、世界を読み解く習慣のことである。 当たり前のことに思えるかもしれないが、その習慣を身に着けることは難しい。 人間には賢い人間ほど囚われてしまう10の本能が備わっているからである。...


書評:『昭和16年夏の敗戦』猪瀬直樹
太平戦争開戦前夜、4年後の敗戦は内閣直属の総力戦研究所に属する若きエリート集団によって予見されていた。 彼らは、奇襲作戦の序盤の有利からの、米国の圧倒的な物量による逆転と戦争の長期化、ソ連の参入すらも予見していたのである。...


書評:『世界標準の経営理論』 入山 章栄
「ビジネスの真理に肉薄している可能性が高い」として生き残ってきた30の「標準理論」が体系的、網羅的にまとめられている。 標準理論を各ディシプリンの中で体系的に位置づけながら、実例を交えて紹介する。 DIAMONDハーバードビジネスレビューの連載をまとめたもので800ページの...


書評:『嫌われる勇気』岸見一郎
どうすれば人は幸せに生きることができるか。 この哲学的な問いに対して本書は、哲人と青年の対話というギリシア哲学の古典的なスタイルを通じて、アドラー哲学に基づくシンプルで具体的な“答え”を共感とともに示してくれる。 アルフレッド・アドラーは、フロイト、ユングと並んで心理学の3...

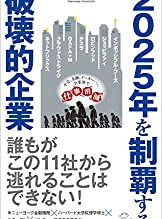
書評:『2025年を制覇する破壊的企業』山本康正
Google、Amazon、Facebook、Apple、Microsoft、Netflix、テスラ、クラウドストライク、ロビンフッド、インポッシブル・フーズ、ショッピファイ。 2021年現在、既存ビジネスへの破壊的イノベーションをもたらし、そのビジネス革新性で世界を席巻す...


書評:『「超」入門 失敗の本質 日本軍と現代日本に共通する23の組織的ジレンマ』鈴木 博毅
本書は第2次世界大戦における日本軍の敗因を分析した名著『失敗の本質』をよりわかりやすく解説した入門書ある。 『失敗の本質』は非常に鋭い文筆で描かれており読みごたえはあるが、読み切るにはかなりの根気とエネルギーが必要である。本書はそれをかみ砕いて、より現代的な文体とストーリー...

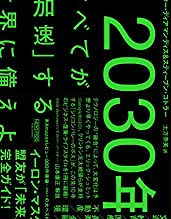
書評:『2030年:すべてが「加速」する世界に備えよ』ピーター・ディアマンディス
本書は、イーロン・マスクの盟友と称されるピーター・ディアマンディス氏が「空飛ぶ車」「老化の克服」「デジタル知性」など10年後の2030年に起きる未来・ライフスタイルの劇的な変化を描く未来予想本である。 テクノロジーによるイノベーションはこれまでも幾度となくディスラプション(...
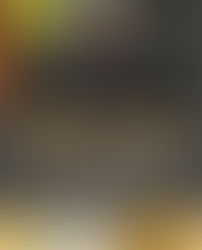
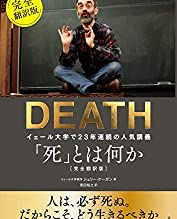
書評:『「死」とは何か イェール大学で23年連続の人気講義』シェリー・ケーガン
人は必ず死ぬ。だからこそどう生きるべきか。 死に対して議論することは、忌み嫌われるものとされている。しかし、死に対して真剣に立ち向かうことなく、恐怖の感情のみを抱くことは心にも体にもネガティブな影響を与えかねない。 この本は、我々が直面しなければならない究極の問題に対して答...


書評:『サピエンス全史』ユヴァル・ノア・ハラリ
筆者は生物学的アプローチでホモサピエンスの歴史を「幸せ」という切り口から考察する。 人類の進化に影響を与えたのが「認知革命」「農業革命」「科学革命」の3つの革命である。 この3つの革命が、人類の運命、そして地球上あらゆる生命の運命にどのような影響を与えてきたか、教養溢れる鋭...


書評:『ザ・コピーライティング――心の琴線にふれる言葉の法則』ジョン・ケープルズ
心の琴線にふれる文章を書くにはどうすれば良いか。 同じ内容を説明するにしても、その見出しやキャッチコピーによって反響は大きく異なる。 売れているコピーには共通している型を学び、多数の実例からその型が実際にどのように使われるかを学ぶことができる。また、反響のなかったキャッチコ...


書評:『ザ・ゴール』エリヤフ ゴールドラット
本書は機械メーカーの工場長を中心に繰り広げられる工場の業務改善プロセスをテーマにした小説である。 この本がアメリカでヒットしてから17年間が経過するまで、日本のビジネスマンがこの本を読むことで競争力を高めることを筆者が恐れて、日本語への翻訳がなされなかったと言われる「幻の名...


書評:『完訳 7つの習慣 人格主義の回復』スティーブン・R・コヴィー
全世界で3,000万部売れた人生論の名著であり、私にとっても最も影響を与えた自己啓発書の一冊である。 この本が教えてくれるのは小手先のテクニックではない。「どのように人生で成功するかについての」人生の普遍のルールである。...


書評:『ストーリーとしての競争戦略』楠木 健
成功を収め持続している企業は、戦略が流れと動きを持った「ストーリー」として組み立てられている。 戦術や戦闘などの現場レベルの施策はそれぞれが個別になされるべきものではなく、戦略と有機的な繋がりをもってなされるべきものである。...


書評:『堕ちたバンカー ~國重惇史の告白~』児玉博
ある天才バンカーの半生を通じて、日本のバブルを描くビジネスノンフィクション。 若手時代から「伝説のMOF担」(MOF担は財務省との窓口となる役割となる重要な役割)として名を馳せ、平和相互銀行事件の処理で「将来の頭取候補」と目され、イトマン事件の内部告発によって「住友銀行の救...


書評:『イノベーションのジレンマ』Clayton M. Christensen
【原書タイトル】The Innovator's Dilemma 技術の目まぐるしい進化が起きている現代において、多くのビジネスマンにとってイノベーションによる既存産業の破壊は対岸の火事ではない。 『イノベーションのジレンマ』は、将来の破壊的技術の出現の脅威への対処法や心構え...


書評:『人新世の「資本論」』斎藤幸平
「資本論」という言葉がタイトルにあると、それだけで拒否反応を示す方もいるかもしれない。 この本では確かにカール・マルクスの思想が取り扱われているが、共産主義を礼賛するような呑気な話ではない。 この本の根底にあるのは、現代においては、資本主義の論理の下で経済活動が最優先され、...


書評:『グロービスMBAクリティカル・シンキング』グロービス経営大学院
以前、会社の研修の一環としてグロービスに通っていた時に参考書籍として薦められて読了。 「考える」という営みを私たちは様々な場面で行っている。 しかし、考えているつもりであったとしても、考え方の深度が不十分であったり、考える方向性が不適切であったるということは少なくない。...


書評:『MBAバリュエーション』森生明
学生インターン時代に、企業の価値がどのように決まるか、その計算プロセスを学ぶことができる入門書。タイトルはMBAバリュエーションとあるが、ある程度財務の知識があれば十分に読み進めることができる入門書。 新聞では毎日のようにM&Aの記事が踊り、「~億円で買収」という記載がなさ...


書評:『論語と算盤』渋沢栄一
ビジネスマンとして数々の業績を残してきて「日本資本主義の父」と呼ばれる渋沢栄一の講演の内容をまとめたものが「論語と算盤」である。タイトルの論語は倫理、算数はビジネスである。 官僚から実業家に転じた渋沢が、資本主義の時代に移りゆくなかで「ビジネスと倫理」をどのように捉えていた...
bottom of page

